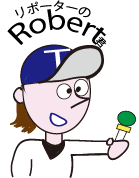こんな疑問やお悩みありませんか?
- 相続ってそんなに難しいの?
- 相続が発生する、本当にもめてしまうの?
- そもそも「相続対策」って何?
お任せください!
松屋の相続支援とは?
その疑問、お悩みや不安
私たちが解決いたします!
やればほぼ確実に効果が出る相続対策を着実に実行
- 松屋のおこなう相続支援コンサルティングは相続の知識を得るもの、教えるものでは有りません。
ご依頼主様のお話を聴きながらほぼ確実に効果の出る相続対策を実行していくことが目的のコンサル窓口として開設しました。
そのためには、障害や不安の根本を探り出し、掘り起こし、取り除き、着実に前に進むことを目的としています。
相続対策において、画期的なノウハウや技術などありません。
また、実行されない対策や施策は、どれだけ素晴らしくても何の意味もありません。
地味ちなコンサルティングで、確実性の高い施策をきちんと実行していくことが大切です。
「そんなの当たり前じゃないか」「そんなことわかっているよ」と言われる方がほとんどです。が、そのほとんどの方が実際にはどの様に実行したらいいのか、誰に相談すればいいのか解っていません。
広告をみて問い合わせて、高額なコンサルフィーを請求されたり、得意分野でない専門士に相談たことで安心し、実は対策になっていなかったりと、実は対策になっていなかったりと、そんな思いや、不安ありませんか?悩んでいませんか?
安心下さい。
私たち相続支援の専門資格者(公認コンサルティングマスター相続専門士・公益財団認定上級相続支援コンサルタント)が、丁寧にお話をお聞きします。
お話をお聴きすることが、コンサルティングのスタートです。
コンサルティングの進め方
-
ー 無料コンサル ー
- まずはお話をお聞きし、コンサルタントが現状を整理します。
- 不安や心配ごとをお聴きし、その原因を探し出し、原因に関する相続の知識をレクチャーします。
(ここまで約2時間30分 無料)
ー 有料コンサル ー
- 個人情報の開示と守秘義務、コンサルティング契約を行います。
- 相続対策案を思案、提示いたします。
- 実行プランの策定
- 実行し、不安の解消を行います。
ひとつひとつ、不安や心配を解消しながら、ひとつひとつ実行していきます。
※ 有料コンサルフィーの価格は、対策事項によって異なります。無料コンサルにおける内容によって、価格を提示させていただきます。金額に合意いただけない場合は無料コンサルで終了となります。
弊社で一貫してコンサルティングを行うので安心してお任せください。
-
毎回のコンサルティング内容を記録いたしますので、いつでも振り返り確認ができます。
コンサルティングが完了しても、いろいろと事情が変わる場合もありますので、お客様専属コンサルタントをつけて都度対応いたします。
遺言書が完成し契約内容の履行完了がされたとしても、お客様との関係は続きます。
相続支援に関する全てをお任せ!
- 当社顧問専門士が ONE TEAM
- 弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士・一級建築士
- 遺言書作成サポート
- 財産目録作成サポート
- 遺言書作成サポート
相続に係ることなら、お困り箇所だけのお手伝いもいたします。
- 相続って何が問題になるのですか?
- 相続は、財産や資産をルール(法律)に従って引き継ぐことです。引き継ぐ方(相続人)の中には、財産がもらえると考えてしまう方もいて、もらえるとなると少しでも多くもらいたいと思ってしまいこれが「争続」の始まりです。被相続人(他界された方)は、相続を家を引き継ぐ考えているため、引き継いでくれる子どもにより多くの財産を渡したいと考えてしまいますが、相続人は個別の財産承継と考えているので、この点に考え方のギャップが生じ、相続人の間で、個と個がぶつかり合ってトラブルが発生、「争続」となってしまうのです。だから相続対策を行っておくことが非常に大切になるのです。相続争いは、小説「犬神家の一族」だけで、自分には降りかからないでほしいですよね。
- 遺言書の書き方だけ教えてほしいのですが、相談できますか?
- 遺言書には「普通遺言」と「特別遺言」とあり、緊急時を除けば一般的には「普通遺言」で行われます。この普通遺言も【1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3.秘密証書遺言】の3種類があります。それぞれに特徴がありますし、書き方も違います。どのタイプの遺言の書式で作成するのが良いのかを含め、書き方に不安や心配があるか方にアドバイスいたします。少しでも不安がある方はご相談下さい。
- 相続の相談をする場合、どんな資料や書類を用意した方がいいのですか?
- 相続をスムーズに行う為には、相続人の確認、財産・資産の確認をする必要があります。戸籍謄本、原戸籍や預貯金通帳、会員権や株式証券・債券・不動産権利証(識別情報)や評価証明書等をご用意いただくことがベストです。たた、はじめは手書きメモでもかまいません。手書きの家系図や資産メモ程度でも大丈夫です。
- 相続人は誰がなれるのですか?
- 相続人になれる人となれない人がいます。基本的には血縁関係で、相続する順番も民法で定められています。でも、必ずしも法律通りにしなければならないことはあまりせん。最低限のルールに従う必要はあります。いろいろと思うことがある方は、是非ご相談下さい。
- 相続って平等にしなければいけないのですか?
- 戦前は家督相続でした。戦後、民法では平等となりました。しかし、100%平等にしなければならないということではありません。例えば現金100万円を3人で平等に分けることは難しいですよね。どの様な分け方をするのかは、相続人のみんなが納得のできる分け方をすることが大事です。「平等」よりも「公平」事前対策やコンサルタントへのご相談をおすすめいたします。お気軽にご相談下さい。
- 相続対策ってなぜ必要なのですか?
- 平等に分ける、公平に分ける、納得のいく分け方をする「分割」や、相続税の納税方法や相続税の控除、節税のルール。より効果的に、トラブルを少なく、トラブルを起こさないために事前に対策を立てておくことが良いことです。誰も損はしたくないですから。
- 相続が開始されても相談できるのですか?
- 相続が開始されると、分割・納税・節税の対策は難しいと思っている方いらっしゃいますが、まだまだ出来ることはあります。あきらめるまえに、一度ご相談下さい。
- 相続に信託を使うのがいいと聴きましたが本当ですか?
- 信託は、信託銀行などが取り扱う商事信託と、個人(家族)間で行う民事信託とがあります。賃貸不動産をお持ちの方や、事業承継をお考えの方は信託を使うのがベストだと商事信託(有料)を利用した対策を進められるケースが多いです。たしかに信託を利用した方が良い場合がありますが、全てが信託を利用した方が良いというわけではありません。信託には信託のメリットもありますが、信託を使わないで他の方法を使った方がいいというケースも結構あります。一度コンサルティンクでのチェックをおすすめします。※ 信託を行う場合でも、信託企業(銀行)に委託せず、民事信託で解決できるケースの方がおおいです。
ご相談者様の声
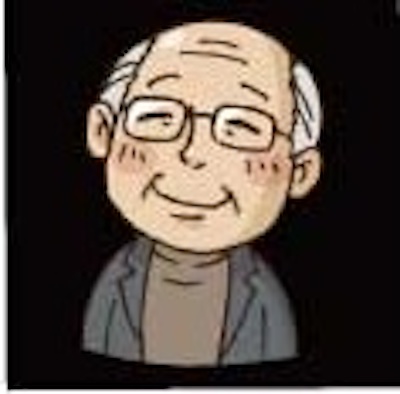
- 80代 母 50代 娘
- 心配でした。本当に親身に相談に乗っていただけるのか。でも、無料コンサルでお話を聴いて、わたしも母も安心して、相続支援を依頼しました。
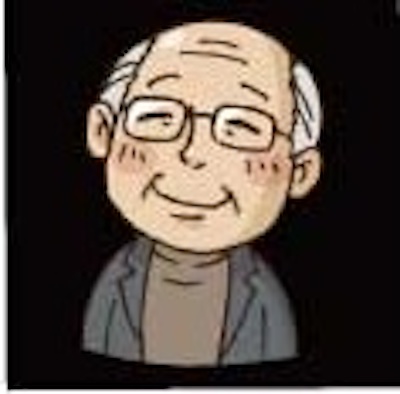
- 60代 男性
- 父のことで相談対策を真剣に考えないといけない時期に、紹介で相談しました。専門士の先生方のアドバイスも聞けて対策に満足です。
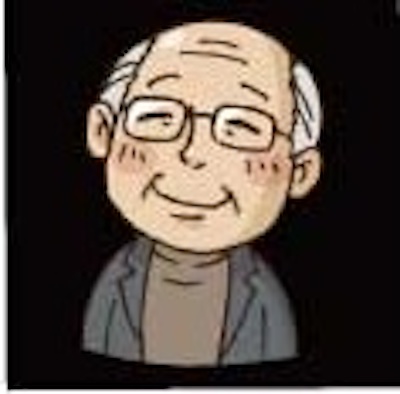
- 80代 男性
- 足が悪いので、自宅に来てもらい相談しました。信託会社から聞いた話の確認のつもりでしたが、家族信託を使う方法を依頼しました。